こんにちは!ねこまるです。
今回は、「宅建士(宅地建物取引士)の勉強法」について、独学で合格を目指す方向けにまとめました。
私はこれまで、公務員試験を始め、複数の資格試験を経験し、働きながら学習を続けてきました。その中でも宅建は「出題範囲の広さ」と「暗記量の多さ」で苦戦する方が多い資格です。
ですが、正しい勉強法を押さえれば 半年以内でも十分合格可能 です。
この記事では、宅建士試験の効率的な勉強ステップ、教材選び、スケジュール管理術まで解説します。)
1. 宅建士試験の特徴を知る
宅建は「法律系資格の登竜門」とも言われ、出題範囲は以下の4つに分かれます。
- 民法(権利関係):14問前後
- 宅建業法:20問前後
- 法令上の制限:8問前後
- 税・その他:9問前後
合格点は毎年35点前後(50点満点)。
つまり、満点を目指す必要はなく「得点源と捨て問を見極める」ことが合格のカギです。
2. 独学での勉強ステップ
ステップ① 基本テキストを1冊決める
- 市販のテキストを1冊に絞る(迷ったら「みんなが欲しかった!宅建士」シリーズがおすすめ)
- 繰り返し読むことが大事。最低3周は必須。
2025年度版 みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 [ 滝澤 ななみ ]
ステップ② 過去問演習
- 過去10年分を繰り返す
- 1問ごと、選択肢ごとに「なぜ正解か/なぜ不正解か」を確認する
- 問題文の読み方に慣れるのが狙い
ステップ③ 苦手分野を重点学習
- 民法は理解が必要なのでYouTubeや参考書で補足
- 宅建業法は細かい数字なども覚えて得点源にする
(宅建業法は受験生の多くが得点源としていることに加え、問題数も多いため、ここで落とすとかなり厳しいです。)
ステップ④ 模試・予想問題で実戦感覚
個人的には、わざわざ追加でお金を払って模試を解く必要はないと思います。不安であれば、宅建の過去問はインターネット上に転がっているため、直前期に時間を測って10年分ほど解くといいでしょう。
- 9月以降は市販の模試を必ず解く
- 本番同様の時間配分(2時間)で練習する
3. スケジュールの立て方
働きながらでも合格できるペースを例示します。
宅建の試験は毎年10月に実施されます。半年での合格を目指すため、4月に勉強を始めるスケジュールを立てると、以下の通りとなります。
- 4〜6月:テキスト読み込み+過去問開始
- 7〜8月:過去問演習を本格化、理解が浅い部分を補強
- 9〜10月:模試で総仕上げ、時間配分の練習
👉 社会人なら「平日1時間+休日3時間」を確保できれば十分です。
4. おすすめ勉強法の工夫
- 通勤時間やスキマ時間はスマホアプリや宅建試験過去問道場(宅建試験 過去問道場🥋 |宅建試験ドットコム)で過去問を解くのがおすすめです。
何度も問題を解くことで、苦手分野がわかり、重点的に勉強すべき箇所が分かります。 - よく「まとめノート」を作る方がいますが、全く必要はありません。労力や時間がかかるに、記憶への定着効果は薄く、時間の無駄です。ノートを作るくらいならテキストを何度も読み込みましょう。
- 問題集は最低3週、できれば5週は解きましょう。一つの問題集を使い続けるのが合格への近道になります。
具体的な回し方は、
①テキストを分野、単元別に読み込む。
②読み込んだ単元ごとに問題集を解く。
③一問ごとに答え合わせ。選択肢ごとにどの部分が誤りなのかを確認する。
という流れで行うと定着しやすくなります。
5. 独学が不安な人向けの選択肢
基本的には、宅建士試験に合格を目指すうえで、予備校などは不要と考えています。
独学で十分に合格が目指せます。ただ、独学が不安な場合は以下の選択肢が考えられるでしょう。
- オンライン講座(スタディング、アガルート、フォーサイトなど)
- 動画講義で理解し、テキストで復習するハイブリッド型が効率的
- 投資額は数万円ですが、時間を買うと考えればコスパは高いと思います。
まとめ
宅建士試験は正しい勉強法を実践すれば、働きながらでも十分合格できます。
- テキストは1冊に絞る
- 過去問の周回を徹底。
- 模試で本番形式に慣れる
この3点を守れば、合格にグッと近づきます。
宅建士の資格は、務める会社によっては手当があり、収入アップにもつながる可能性があります(残念ながら、ねこまるの職場ではありませんが…)。これから受験される方は、ぜひ参考にしてくださいね!
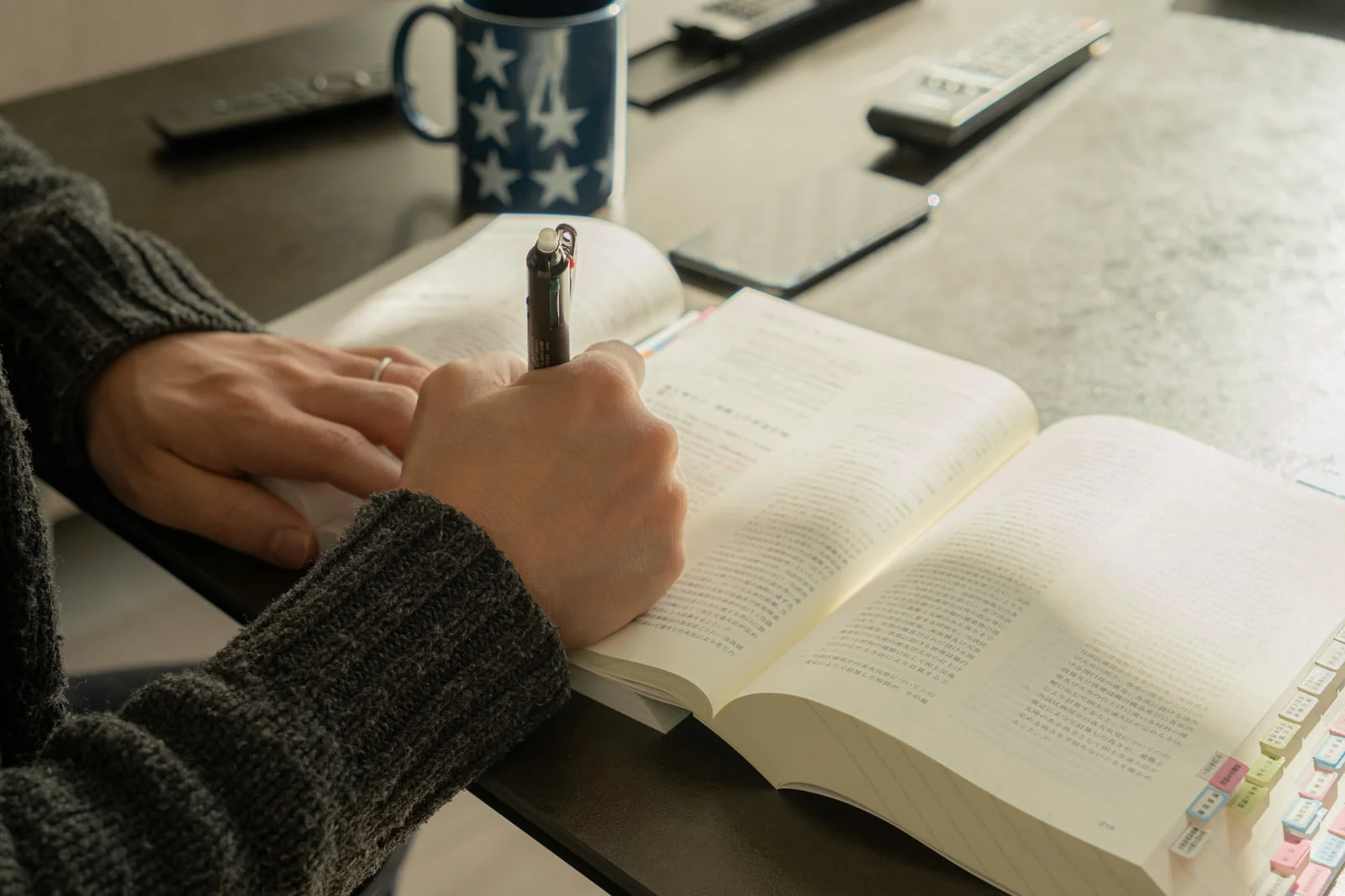

コメント